大切な愛猫のもしもに備えた対策を。猫グッズ作家「straycat.lady」を訪ねてみた。

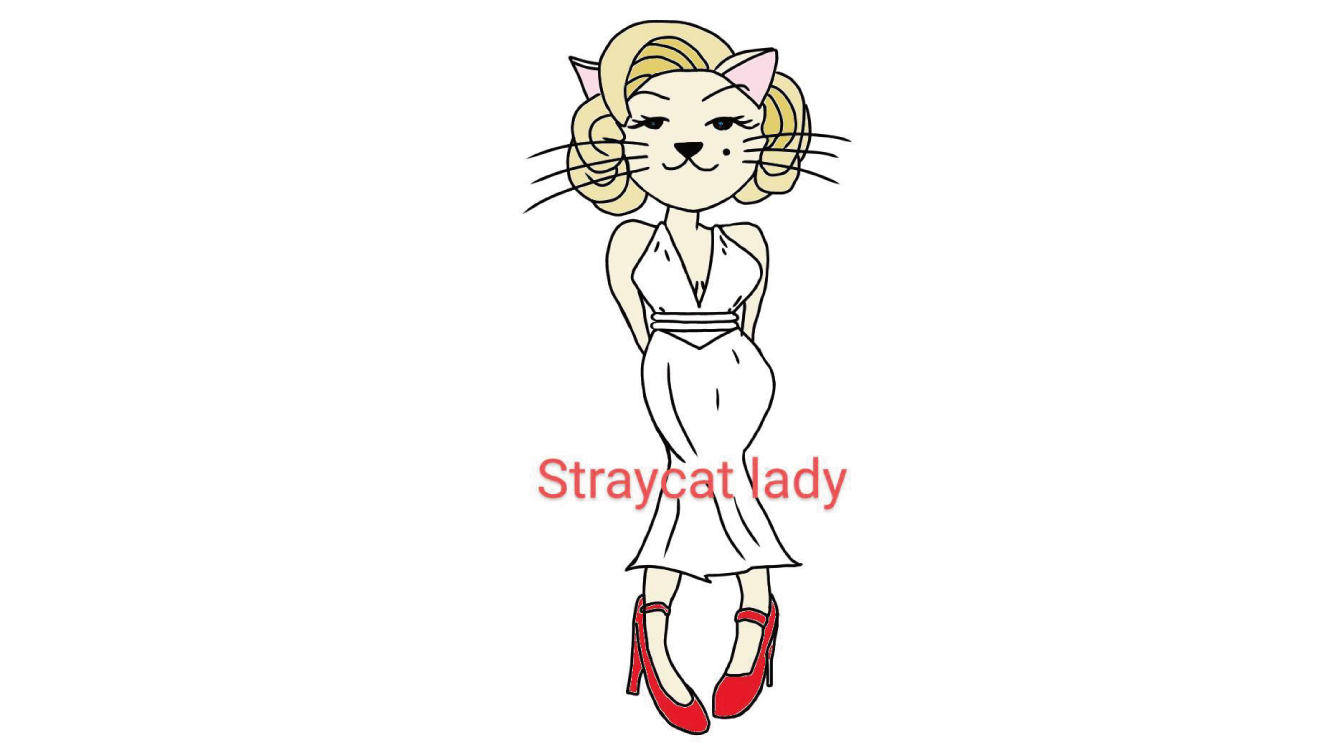




マルシェへの出店を中心に活動しており、ハンドメイド作品の販売を通して、愛猫の「もしも」に備えた対策の大切さを伝えている。今回は、愛玩動物救命士やペット災害危機管理士などの資格を持つ久島 奈保子(きゅうしま なおこ)さんに、活動のきっかけから、その先に広がる展望まで、幅広くお話をうかがった。
- 忘れられない出来事が、使命に変わるまで
- “猫社員”と共に、妥協なきものづくり
- 社会貢献に向けた、温かいコミュニティ活動
- 未来へつなぐ「愛の連鎖」
①忘れられない出来事が、使命に変わるまで
愛するペットとの暮らしは、私たちに多くの喜びと癒しを与えてくれる。しかし、もしその大切な家族が突然いなくなってしまったら?ーーそんな「もしも」の不安に寄り添い、可愛らしい首輪やスタイの制作・販売を通じて猫と飼い主の絆を深める活動をしているのが久島さんだ。
およそ10年前、久島さんは動物保護団体から猫を引き取ったことをきっかけに、猫の魅力にすっかり夢中になった。しかし、その幸せな日々は、ある日突然一変する。少し目を離した隙に、愛猫が家から逃げ出してしまったのだ。
「頭が真っ白になりました。仕事に行く前も、帰ってきてからも、ずっと愛猫のことを考えていました。休みの日は一日中、探し続けました。毎日が後悔の連続で、ろくに眠れない日々が続きました。」
チラシを配り、近所の人に声をかけ続ける日々。その中で、久島さんは見ず知らずの人々の温かさに触れる。「今時間があるから、一緒に探しますよ」と、多くの人が手を差し伸べてくれたという。その結果、脱走から1ヶ月後、ついに愛猫と再会することができたのだ。その時の感動と人々への感謝は、久島さんの心に深く刻まれた。
この経験は、二つの大切なことを教えてくれたという。一つは、愛猫が迷子になることの恐ろしさ。そしてもう一つは、地域の人々の温かさという「見えない絆」の力だ。
「もう二度とこんな想いをしたくないし、私と同じような経験を、他の誰にもしてほしくないと思いました。もし迷子になってしまっても、ちゃんと飼い主さんのもとに戻れるよう、『連絡先が書けるような可愛らしい首輪』を作りたいと思ったんです。」
これが、straycat.ladyの原点である。久島さんは、この経験を単なる個人的な出来事で終わらせるのではなく、猫を愛する人々の心の支えとなるような活動を通して、同じ不安を抱える人々の助けになりたいと強く願うようになったのだ。

② “猫社員”と共に、妥協なきものづくり
久島さんが制作する首輪やスタイは、単なるおしゃれなアクセサリーではない。それは、万が一の時に「うちの子だとすぐにわかる」ためのお守りであり、猫と飼い主の絆を深めるための大切なツールなのだ。
リボン制作を始めたのは、今から約2年前。会社員として働く傍ら、まずはマルシェでの活動を開始した。当初は縫製の知識も技術も全くなかったそうだが、専門のリボン教室に通い、講師資格を取得するまで情熱を注いだ。そして、その技術を活かして、猫専用の首輪やスタイを開発する日々が始まった。
久島さんのものづくりを支えているのは、共に暮らす5匹の愛猫たちだ。彼らは“猫社員”として、新作グッズの試作品を厳しくチェックする重要な役割を担っている。
「人間がいいと思って作っても、猫が嫌がったら意味がありません。裏地がゴワゴワしていたり、ゴムの伸びが悪かったり、少しでも『嫌だ』という仕草を見せたり、すぐに取ろうとしたりしたら、その試作品は不採用になります。たとえ完成していても、全て作り直します。猫は本当に繊細なので、我が家の猫のチェックをクリアしたものだけをお客様へお届けしています。」
この徹底したこだわりは、久島さんが持つ「愛玩動物救命士」としての専門知識に基づいている。猫の身体構造や行動特性を深く理解しているからこそ、首輪が猫の健康を損なわないよう細心の注意を払うのだ。猫の首に負担がかからないよう、軽くて柔らかいマスク用のゴムを使用したり、肌に当たる部分は優しいフェルトで覆ったりと、細部にまで猫への愛情が詰まっている。また、万が一何かに引っかかっても、すぐに外れる「セーフティ仕様」も、安全性を第一に考えた結果である。
「目に見える部分はオシャレなデザインに、猫に触れるような目に見えない部分は、縫製や安全性などに細心の注意を払っています。そして、お客様にはこのリボンに必ず名前と連絡先を書いてもらうのが、私との約束事です。そうすることで、もし迷子になってしまっても、誰かに見つけてもらえれば、飼い主さんと連絡を取ることができ、必ずお家に帰れるんです。」
購入したものを長く大切に使ってもらうためにも、品質への妥協はせず、日々改良を重ねている。
「何度も付け替えて、何度もスキンシップを取ることで、一緒に写真を撮ったり、家族みんなで笑ったりする時間が増えていきます。そして、いつか悲しい別れが来たとしても、このリボンを見た時に『たくさん愛したね、たくさん遊んだね』と、良い思い出が溢れる大切なものになったらいいな、と思っています。」
愛猫の「もしも」に備えた対策だけでなく、「我が子の最期の日まで穏やかな生活が続くように」と願いを込められているという。これは、「愛玩動物救命士」として、猫の身体構造や行動特性を深く理解している久島さんの専門知識と、昨年愛猫を見送った実体験に基づいた言葉でもある。
③社会貢献に向けた、温かいコミュニティ活動
久島さんの活動は、ものづくりを超え、多くの人々の心に寄り添う、温かいコミュニティを築き上げている。マルシェでの対面販売では、商品を売るだけでなく、猫を飼う人々の悩みに耳を傾け、時には解決策を提案する。
「お客様の悩みを聞くのが好きなんです。『うちの子は首輪を嫌がるから…』という声もよく聞きます。でも、一人で悩まないでほしい。飼い主さんには、猫と向き合う『根気』が大切だと伝えています。自分の子どものトイレトレーニングと一緒で、ゆっくり時間をかけて、段階を踏んで、少しずつ慣れさせてあげれば、どんな子も必ずできるようになります。」
言葉が話せない動物たちと心を通わせ、気持ちを読み取る「アニマルコミュニケーター」の資格を持つ久島さんは、猫の性格を紐解き、飼い主とのより良い関係を築くためのアドバイスも行っている。「なぜこの子は懐かないんだろう?」「どうしてこんなに素っ気ないんだろう?」といった飼い主の悩みを解決し、猫との絆をさらに深めるお手伝いをしたいと語る。
また、久島さんは、ペット災害危機管理士としての専門知識を活かし、災害時のペット避難を考える「ペット防災」の啓発活動にも力を入れ、行政との連携も模索中だという。
「飼い主さん自身が、もしもの時にどうすればいいかを知っていることが何より大切なんです。いざという時に慌てて準備するのではなく、今からできることを考えてほしいです。」
猫も防災時にハーネスをつけて歩く練習をしてほしいと語る一方で、猫はハーネスを嫌がることが多いため、まずは軽いリボンから慣れさせる「ステップアップ防災」を提唱する。
「猫にハーネスをつける文化はまだあまり認知されていないので、私自身の技術面でも、飼い主さんの意識面でも、まだ時間がかかるだろうなと感じています。これが今後の課題ですね。岐阜ではまだまだ知られていませんが、災害時に猫を一時預かりできる環境を、地域ごとに作っていくのが目標です。」
自身の経験と知識を活かして、悩みに寄り添い、「もしも」のときの不安を少しでも減らすために、久島さんは地域に根差した活動も大切にしている。

④未来へつなぐ「愛の連鎖」
久島さんが制作する猫グッズは、負担が少なくはじめてにぴったりのチョーカーや襟付きネクタイ、個性豊かなスタイや麦わら帽子など多岐にわたる。この制作活動の先にある展望についても語ってくれた。
「将来的には、これらの制作を福祉施設の方々にお願いしたいと考えています。素晴らしい縫製技術を持った方々が、適正な賃金でやりがいのある仕事ができるような仕組みを作りたいです。私の活動が、猫だけでなく、人々の笑顔にもつながれば嬉しいです。」
猫を大切に思う気持ちが、迷子の猫を見つけた人々の行動につながり、その行動が猫を家族のもとへ帰す。この「愛の連鎖」を支えるのが、久島さんが一つひとつ心を込めて作るリボンだ。この小さなリボンは、猫の命を守るだけでなく、人と人との優しい交流を生み出すきっかけにもなっている。
久島さんの活動は、猫を愛する気持ちから始まり、今や、多くの猫と飼い主、そして社会全体を巻き込む大きな輪へと広がりつつある。今日もどこかで、大切な命と、誰かの「笑顔」を守り続けているのだろう。

詳しい情報はこちら

 山県市
山県市 














