モノづくりを通じて人と人がつながる場所「Craft Comune」を訪ねてみた。






クラフトバンドを使用した、手作りのバックや小物、アクセサリーの制作・販売を手掛けている。
今回は小森 祐月(こもり ゆづき)さんに設立の経緯やビジョンをうかがった。
- モノづくりを中心に、みんながつながる場所に
- つながりを生み出す場として、屋号に込めた想い
- 日常に寄り添う、やさしくて強い手仕事のかたち
- 岐阜の風土を活かした作品づくり
- 届け方を探して、つながりの場を育てる
①モノづくりを中心に、みんながつながる場所に
牛乳パックや新聞紙などの再生紙から生まれる「クラフトバンド」。平たい紙ひもを使って、手だけでかごやバッグを編み上げるこの技法は、ハンドメイド素材として多くの人に親しまれている。紙とは思えないほど丈夫でしなやか。色の組み合わせや編み方によって多彩な表情を見せるのも魅力のひとつだ。
このクラフトバンドに魅せられ、日々作品づくりに取り組んでいるのが「Craft Comune」の小森さん。制作の原点には、家族とのあたたかな記憶があるという。
「母も祖母も、家でいろんなものを手作りしていたんです。蔓のかごやトールペイントなど、趣味の範囲ですが、よく何かを作っていました。私が学校から帰ると、手を動かしながら『お帰り』って迎えてくれて。そんな光景が日常でした。」
子どもの頃から、自然と“ものづくり”が身近にあったという小森さん。ビーズ、刺繍、ミシンなど、さまざまな手芸を試したが、なかなか長続きしなかったそうだ。そんな中、クラフトバンドに出会った瞬間、「これだ」と直感した。
「とにかく、楽しいんです。夢中になって手を動かしていると、心が落ち着いていく感じがします。嫌なことがあった日も、気持ちの整理をしたいときも、編んでいると自然と整っていくんですよね。」
岐阜県揖斐川町・春日地区(旧・春日村)出身の小森さん。山あいの自然に囲まれて育った彼女にとって、「かご」は昔から暮らしの中にある存在だった。
「近所のおじさんも、おばさんも、畑仕事や薬草採取、お茶摘みの時などに、自分たちで編んだかごを使っていました。子どものころはその風景が当たり前すぎて、特に興味はありませんでした。でも、大人になってふと『かごを作ってみたい』と思ったんです。すぐクラフトバンドの教室探して、通い始めました。」
自然の中で暮らし、手を動かし、静かに自分の時間を紡いでいく。クラフトバンドは、小森さんにとって“道具”であると同時に、心を整えるための癒しの存在でもある。作るよろこびは、今日も静かに日々を支えている。

②つながりを生み出す場として、屋号に込めた想い
クラフトバンドとの出会いをきっかけに、自らの手で道をひらいてきた小森さん。前職は医療事務だったが、家庭や子育てと両立できる働き方を模索するなかで、「自分のペースでできるものづくり」を軸に個人事業としての道を選んだ。
屋号に掲げたのは「Craft Comune」。Comuneはイタリア語で“共同体”を意味する言葉だ。
「作品を通じて、人と人がゆるやかにつながっていくような“集まれる場所”をつくりたいと思ったんです。自分が作ったもので誰かが喜んでくれて、またそこから誰かと出会う。そんな風に、コミュニティが生まれていくといいなと思って名付けました。」
ロゴに描かれているのは、故郷・春日村の森にある切り株。そのまわりに人が集まり、物語が育まれていくそんな世界観を表現している。
「山の中で育ったので、木や草花は本当に身近な存在でした。大きな木があって、それは見えないところで大きな根っこに支えられている。モノづくりも、そんな風に“根”があってこそ続けられるものだと思うんです。ロゴには切り株を描いて、そこに人が自然と集まってくるようなイメージを込めました。」
小森さんにとって「コムーネ」は、単なる屋号ではなく、自身の願いと生き方そのものを表す言葉でもある。自然の根が木を支えるように、ここに集うすべての人のつながりを生み出していく。
③日常に寄り添う、やさしくて強い手仕事のかたち
小森さんが手がけるクラフトバンドのかごは、その可愛らしい見た目や温かみのある風合いに加え、軽さと丈夫さを兼ね備えている。日々の買い物バッグとしてはもちろん、パン屋やケーキ屋の商品ディスプレイに使われることもあるという。
「やさしい雰囲気だから、店舗の空間にも自然になじんでくれるんです。しかも、ちゃんと自立するから商品をきれいに引き立ててくれて。見た目だけじゃなくて、実用的な面でもすごく優れていると思います。」
印象的だったのは、スーパーのカートほどの大きさの買い物バッグを制作したというエピソード。荷物をたくさん入れても壊れず、柔らかい素材ゆえに扱いやすく、生活にやさしくフィットする。
「プラスチックみたいに硬くないから、ぶつかっても安心なんです。たくさん入れても平気ですし、何より軽いのが魅力ですね。」
クラフトバンドは、夏のイメージがあるが、実際には一年を通して使える。日常の装いにも馴染むよう、デザインには細やかな気配りを重ねているという。
「着物にも洋服にも合うようなデザインにしています。普段の装いにも取り入れてもらえるように心がけています。」
単色でシンプルに編むだけでなく、複数の色を組み合わせたり、模様を織り込んだりと、その技法は多彩。日本ならではの繊細さと丁寧さが、細部にまで宿る。
「外国の方にも見ていただきたいです。日本のハンドクラフトは海外でも高く評価されていますし、『日本にはこんな手仕事があるんだ』と知ってもらえたら嬉しいですね。」
小森さんの作品は、かごバッグとして日常に寄り添ったり、子どものおもちゃ箱になったり、お店のディスプレイに使われたりと、暮らしの中に溶け込み、生活を豊かにしていく。
④岐阜の風土を活かした作品づくり
クラフトバンド教室に通い始めた頃から、小森さんはマルシェへの出展を続けている。最初はポシェットなどの小さな作品から始まり、かごやアクセサリーなど、少しずつ作品の幅を広げていった。
「クラフトバンドに、地元の草木や素材を組み合わせてみるのが好きなんです。私なりの視点を加えて、作品にしていくのが楽しいです。」
小森さんの作品に息づいているのは、春日の自然。地域の草木や染料を生かすことで、どこにもない表情の作品が生まれている。最近では、草木染めにも挑戦しているという。
「地元の草花で草木染めをしてみたり、春日にある素材を試してみたりしています。池田町にある柿渋を活用した商品を販売している方とご縁ができて、『この素材で何か作ってくれない?』と言っていただいたことをきっかけに、柿渋染めのかごづくりにも取り組んでいます。」
使う素材も、発想のヒントも、日々の暮らしのなかにある。子どもの遊びからインスピレーションを得ることもあるそうだ。
「ある日、子どもがヨウシュヤマゴボウの実を拾ってきて、それを潰して遊んでいたんです。それを見たときに、『あ、これ染めに使えるかも』ってひらめいて。日常の中で自然にヒントが湧いてくるのが面白いです。」
こうした日常の中にある小さな発見が、制作意欲を引き出してくれる。子どもと過ごす時間や、季節の変化が、アイデアの源泉となっているのだ。自然と共にある暮らしが、小森さんの創作をやさしく支えている。

⑤届け方を探して、つながりの場を育てる
クラフトバンド作家は全国に数多く存在し、オンライン販売サイトでも日々さまざまな作品が出品されている。そんな中で、自分の世界観を伝え、作品を届けていくことは決して簡単ではない。
「今いちばん悩んでいるのは、“Craft Comune”をどうやって知ってもらうかということです。委託販売やネットショップの利用も続けていますが、自分の作品の雰囲気をきちんと伝えるにはどの方法が合っているのか、今まさに模索中です。」
そんななか、SNSで小森さんの作品を知り、「どうしても欲しい」とマルシェに足を運んでくれたお客様もいた。そのひと言が大きな励みとなり、制作過程の動画や情報発信にも少しずつ取り組んでいる。
今後、特に力を入れたいのが定期的なワークショップの開催だ。これまでにもマルシェや友人宅、レンタルスペースなどで体験会を行ってきた。好評だったこともあり、今後は定期開催や連続講座の構想も進んでいる。
「クラフトバンドのかごって、完成までに結構時間がかかるんです。なので、1回きりではなく、4回くらいに分けて作っていくスタイルが合っていると感じています。ただ作るだけじゃなくて、その過程で人とのつながりができていくことが、なにより嬉しいです。」
自分の作品をきっかけに、誰かの暮らしに彩りが加わり、新しい出会いが生まれる。その循環の中で、“Craft Comune”という名前とともに、小森さん自身の存在も思い浮かべてもらえるようになりたいという。
「最終的には、かごを見ただけで“あ、Craft Comuneのかごだね”って言ってもらえるようになりたいです。そうやって、作品を通してみんなとつながっていく場をこれからも育てていきたいと思っています。」

こだわりとあたたかさの詰まったクラフトバンドの作品は、日々の暮らしにやさしい風合いを添えてくれる。マルシェへの出展予定や作品の紹介はInstagramで発信中。興味をもった方は、ぜひその世界にふれてみてほしい。
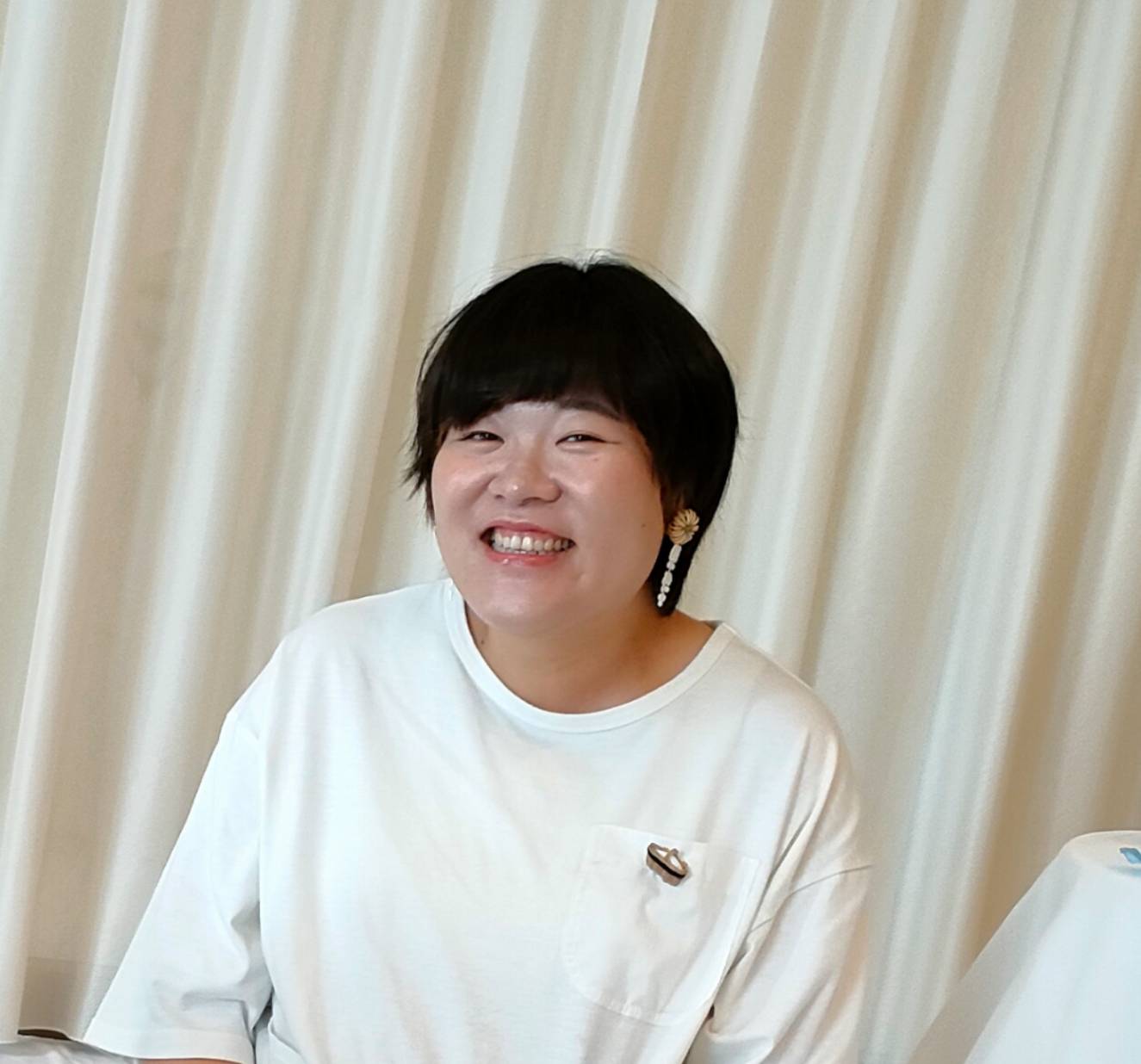
詳しい情報はこちら

 揖斐川町
揖斐川町 














