一瞬のきらめきをガラスに込める「海波硝子」を訪ねてみた。

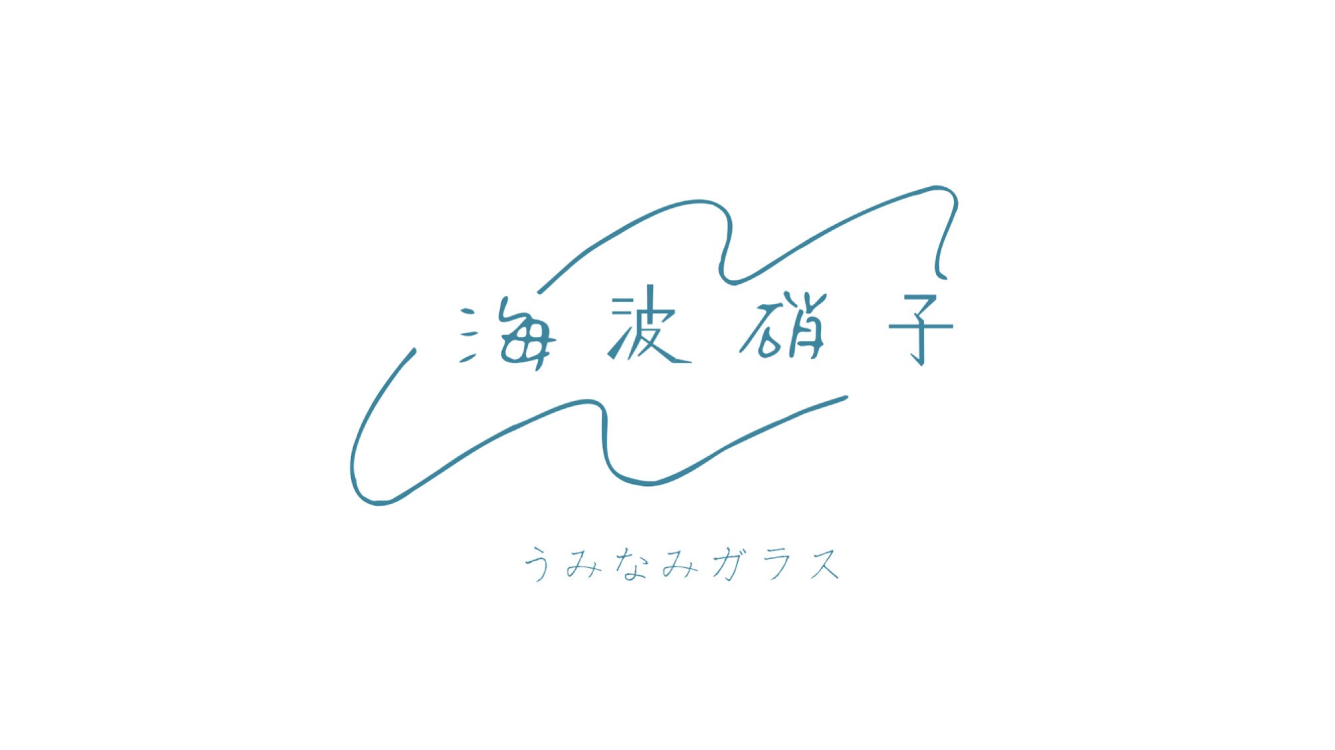




今回は、岐阜県出身で、作品展などを岐阜で開催しているガラス作家の若杉 海央(わかすぎ みお)さんに、創作の背景やガラスへの想いをうかがった。
- 「海」と「波」に込めた、自然への想い
- 富山での学びを礎に、独立へ踏み出した決意
- 「唯一無二」の作品を生み出すこだわり
- 届けたいのは「好き」を共感できる人
- 活動の場を広げ、ガラスの魅力を伝えたい
①「海」と「波」に込めた、自然への想い
富山県富山市を拠点に活動を行い、岐阜でも作品展を開催するなど「海波硝子(うみなみがらす)」として精力的に活動している若杉さん。その名前には、自身の創作活動の核となる想いが込められている。
「私の名前に『海』が入っているので、昔から海に親しみを感じていました。制作する作品も、海や空など自然をモチーフにすることが多かったので、『海』という文字は絶対に入れたいと思っていたんです。」
そう語る若杉さんの作品の原点には、「一瞬の美しさをガラスに閉じ込めたい」という強い想いがある。
「空の雲や海の波が、一瞬で色や形を変える。その美しい瞬間をガラス作品として残しておきたいという想いがずっとあり、制作に取り組んできました。私が感じた自然の美しさを、作品を通して多くの人に伝えたいと思っています。」
そんな作風を表すように「海波(うみなみ)」という言葉を選び、そこに制作するものが伝わるよう「硝子」を重ねた。こうして屋号「海波硝子」が生まれたのである。
吹きガラス制作との出会いは中学生の頃。滋賀県長浜市にある黒壁ガラス館を両親とともに訪れた際のことだった。
「母もガラスが好きだったので、生活の中でもガラスは身近な存在でした。私自身も幼い頃から透明で美しいものが好きでしたが、ガラス館へ連れて行ってもらった時に、吹きガラスの制作風景を見て、強く惹かれたんです。」
ガラスが好きだったというお母様の影響も受けながら、その世界に足を踏み入れ、技術を磨いてきた若杉さん。独立にあたって選んだ「海波硝子」という名前には、自身のルーツへの想いが込められている。


②富山での学びを礎に、独立へ踏み出した決意
高校卒業後、若杉さんは富山県富山市にある富山ガラス造形研究所へ進学した。富山市は「ガラスの街とやま」として街ぐるみでガラス文化を育んでおり、その環境の中で基礎から表現の幅を学んでいった。卒業後はガラス作家のアシスタントとして活動し、作品づくりを支えながら技術を重ねていった。
しかし、次第に心の中に「自分の作品を世に出したい」という気持ちが芽生え始める。
「修行時代はさまざまなことを教えていただき、本当に貴重な経験になりました。作家の活動をそばで支える中で、ひとりのガラス作家として、自分の名前で作品を発表したい、自分の表現を追求したいという想いが強くなっていったんです。」
しかし、アシスタントから独立するには大きな決断が必要だった。自分の手で作ったものを作品として届けたいという想いを抱えつつも、踏み出すきっかけをつかめずにいた。そんな折、富山を離れ大阪に移り住むことになった。
「大阪では自分の作品に向き合う時間をしっかり持てるようになりました。修行で得た技術を活かして制作を続けていると、やっぱりガラス作家として活動していきたい気持ちがどんどん高まっていったんです。」
学校での学びも、修行時代の経験も、そのすべてを貫いていたのはガラスへの愛着だった。子どもの頃から透明で美しいものに心を奪われ、ガラスの輝きに魅了され続けてきた。その想いが揺らぐことはなく、むしろ独立への道を開く力となった。
こうして富山で培った技術を土台に、本格的に自分の作品制作を開始。屋号「海波硝子」として作品を世に送り出すようになった。表現者として、自分の感じた美しさを多くの人へ伝えるために、若杉さんは今日もガラスと向き合い続けている。

③「唯一無二」の作品を生み出すこだわり
若杉さんの作品は、日常で使えるグラスや花器から、芸術性の高い美術品まで多岐にわたる。
「すべて一人で制作しているので、細かい仕事や時間をかけた制作ができるのが強みです。手間がかかることも多いですが、手作りだからこそ、一つひとつ丁寧に、魂を込めてつくっています。」
安価で手に入りやすいガラス製品が増えている現代において、量産品にはない手作りならではの価値を大切にしている。そのため、一つの作品を完成させるまでに一年ほどの時間をかけることもあるという。手間暇を惜しまず、丁寧に作品と向き合うことが、若杉さんのものづくりの原点となっている。
さらに、自身の作品が、ガラス業界のプロから見ても評価されるものでありたいという想いがある。
「ガラスに詳しい方が見ても、きちんと技術があるとわかるようなものをつくりたいと思っています。少しも妥協せず、細部までこだわり、ひとつずつ丁寧に作っています。」
若杉さんの作品には、ガラスの透明感や美しさに加えて、技術者としての強いこだわりが込められている。ガラス制作を始めた当初から好きだった透明感を最大限に活かしつつ、真似のできない唯一無二の作品を生み出すこと。それが、若杉さんの作品の最大の魅力だといえるだろう。

④ 届けたいのは「好き」を共感できる人
若杉さんは、自分と同じように自然の景色やその一瞬の美しさに心を動かされる人や、海や空に魅了されている人に、作品を通じて感動を共有したいと考えている。
「万人受けを目指すのではなく、私の作風を好きだと感じてくれる人に刺さればいいなと思っています。同じ感性を持った人に届けたいです。」
ガラス製品の魅力は、素材の透明感や高級感、重さ、そして多様な技法にある。グラス一つにしても、素材そのものが好きな人、特定の形や色に惹かれる人など、様々な「好き」があることを理解し、そうした一人ひとりの「好き」に寄り添いたいという想いを強く持っている。
「ガラスに興味を持っていなかった人にも、『なんだかいいな』と感じてもらえるような作品作りを大切にしています。作品を見て、『このグラスで家族と一緒にお酒を飲みたいな』とか、『ここにこんな花を生けたいな』とか想像してもらえると嬉しいです。」
もともとは美術品をメインに制作していたが、現在は普段使いできる器や花器にも力を入れており、グラスや花瓶、書道具、ペンレストといった作品を制作し、日常に取り入れやすい形を追求している。
グラスは手に持ったときに手に馴染むようなデザインを、花瓶は花を生けたくなるような佇まいを目指している。美術品的な表現を残しつつ、日常使いできる作品を通じて、ガラスを身近に感じる人々とのつながりを築こうとしている。
これは、ガラス作品をより身近に感じてほしいという想いからだ。
「普段使いできるものを通して、ガラス作品に親しみを感じてもらいたいと思っています。気軽に作品を手に取ってほしいです。」
自分の感性を信じて生み出した作品が、同じ「好き」を共有する誰かの日常に溶け込み、喜びや感動が伝わっていくことを目指している。


⑤ 活動の場を広げ、ガラスの魅力を伝えたい
今後は、自身の表現を追求し、作家としての活動を広げていきたいと語る若杉さん。飲食店にグラスの提供をするなど、手に取ってもらえる機会を増やし、より多くの人に海波硝子の魅力を知ってもらいたいと考えている。手にした人が作品に興味を持ち、ブランドの認知が高まることを目指している。
そのためには、ネットショップの充実や販売強化はもちろん、個人名での発表の場も作っていきたいという。
「今まではグループ展を中心に参加してきましたが、個人での展示にも挑戦していきたいです。『海波硝子 ワカスギミオ』という名前をもっと広げていけたらいいなと思っています。」
若杉さんが目指すのは、自身の作家活動を確立することだけではない。ガラス作品の魅力をより多くの人に伝えていくことも重要な目標だ。これまでガラスに縁のなかった人にも、ガラス作品の奥深さを伝えるため、作品の裏側にある制作過程を見せることも大切にしている。
「私自身ガラスの世界に身を置いて、完成作品だけでは技術や魅力が伝わりにくいと実感しました。SNSを活用して、どういう工程で作品が完成するのかという部分まで、発信していきたいと思っています。すべては、より多くの人にガラスの魅力を伝えるためです。」
作家として活動を続けられているのは、仕事を依頼してくれる人々や支えてくれる周りの環境があってこそだと、改めて実感しているという。そうした感謝の気持ちを胸に、ガラスの魅力をより多くの人に伝えていきたいと若杉さんは語る。
自身の表現を追求しながら、ガラスという素材の可能性を発信していく若杉さんの歩みは、これからも続いていく。

詳しい情報はこちら

 大垣市
大垣市 














