伝統と革新が共存する創業160年超の老舗「田中屋せんべい総本家」を訪ねてみた。

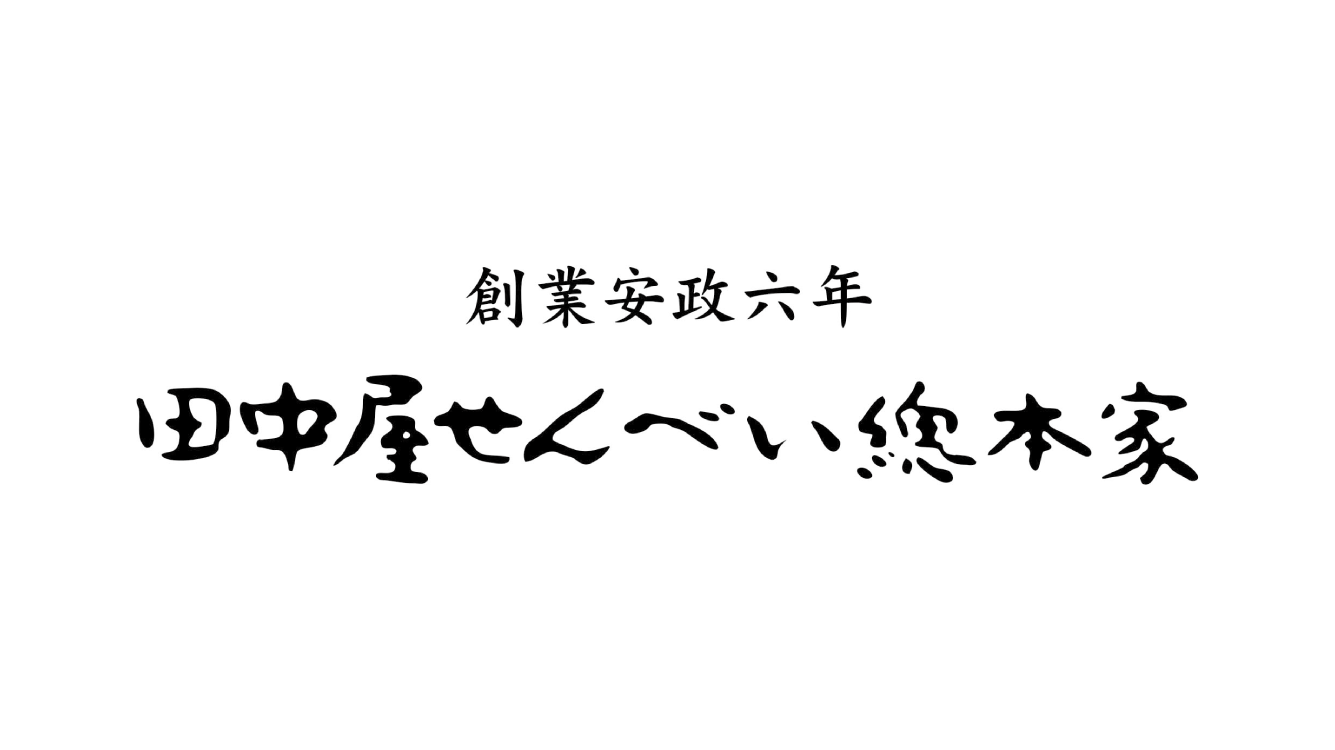




創業は安政6年にまでさかのぼり、名物元祖、みそ入大垣せんべいで知られる老舗である。今回は、6代目代表取締役の田中 裕介(たなか ゆうすけ)様に、経営哲学や業界のこれからについてお話を伺った。
- 老舗を継ぐという選択
- 「再発見」を繰り返し、伝統をアップデート
- 蘇った創業当時の屋号「玉穂堂」
- 変化に対応し、進化し続ける組織
- せんべいの新しい価値を創る
①老舗を継ぐという選択
創業160年以上の歴史を持つ田中屋せんべい総本家の6代目社長を務める田中社長は、家業を継ぐことに特別な葛藤はなかったと語る。それは、家業に携わるのが当たり前の環境に置かれていたからだ。
「生まれた時から両親も周囲の方々も、当然将来は私が後を継ぐと思っている環境だったので、気づいた時には、自然と『自分が継ぐんだ』という意識になっていたと思います。」
その言葉には、幼い頃から宿命のように感じてきた家業への想いが滲み出ていた。しかし、その道のりは決して平坦なものではなかった。
修行のために家を離れ、3年間和菓子職人として腕を磨いた後、2001年、27歳の時に実家である田中屋せんべい総本家へ入社した田中社長。だが、そこで見たのは、せんべい事業に可能性を見出せず、洋菓子事業に注力していた先代の姿だった。せんべい事業は下火になり、廃業の危機さえ感じさせる状況だったという。
「父は私に他の商品に挑戦してほしかったようですが、私はせんべい屋として継ぐ気持ちで修行を積んできたので、自分の意思を貫き通しました。」
とは言え、試行錯誤を重ね奮闘する先代を目の当たりにして、将来の不安は拭いきれなかったという。ただただ心にあったのは「なんとか立て直さなければ」という気持ちだけ。その危機感と強固な意志が、田中社長を突き動かし、老舗再建への道を歩み始めたのだ。


②「再発見」を繰り返し、伝統をアップデート
田中社長が最もこだわったのは、受け継いだ伝統をそのまま踏襲するのではなく、「再発見」すること。単に教えられた通りに作業を繰り返すだけでは、今までと何も変わらないと思ったのだ。
「出来上がった事業をただ受け継ぐだけでなく、自分のものにするために、なぜこうなるのか、この工程ではどんな工夫が必要なのか、といったことを再発見する必要があると思ったんです。20年かけてひとつずつ辿り、再発見を繰り返してきました。」
「再発見」の哲学は、製品の隅々にまで行き渡っている。伝統の「味噌せんべい」に使用する4つの原材料(粉、砂糖、味噌、ごま)は、25年前と比べて産地もクオリティも異なるものにすべて刷新した。
「味噌せんべいの原材料が“粉、砂糖、味噌、ごま”の4つだけということは、25年前と変わりません。ですが、ひとつとして同じ材料は使ってません。」
現在は地元岐阜県産の素材にこだわり、伝統の味に仕上げている。その背景には、どんな状況でも事業を継続し、従業員の生活を守るという、経営者としての強い責任感があった。
「外国産の材料を使っていると、戦争が起きたり、海外との貿易トラブルが起きたりした時に、生産が不安定になってしまいます。商売を続け、従業員の生活を保証するためにも、そういったリスクは避けるべきだと考え、地元岐阜県産の材料に辿り着きました。」
田中社長は、常に市場と顧客という「出口」から逆算して考えているという。安定した販売先を確保するための戦略的な一手として、2023年にカフェ事業「田の中屋」を立ち上げた。
「いずれは原材料の生産も自社でできる環境にしていきたいと思っています。カフェ事業はその足掛かりでもあり、地域とのつながりをつくる拠点といった役割も担っています。」
伝統を守り続けることとは、同じことを繰り返すことではない。時代や社会の変化に合わせて、常に素材や製法、そして経営をアップデートしていくこと。それが田中社長が創り出す「伝統」なのだ。


③蘇った創業当時の屋号「玉穂堂」
6代目が新たに作った商品として「玉穂堂(たまほどう)」という一口サイズのせんべいがある。
実は商品名の「玉穂堂」は、創業当時に使われていた屋号でもあるという。まるで原点に立ち帰るような気持ちで作られた商品であるとともに、歴史ある屋号に新しい息吹を吹き込み、リブランディングを図るための試みでもあった。
「私が開発した新しい商品を売り出すとなった時に、田中屋せんべい総本家ブランドで出しても魅力が伝わりにくいかも、と思ったんです。思い切って、長年使われてなかった『玉穂堂』という屋号を使うことにしました。」
初代がみそせんべいを作り上げたように、6代目が新たに作り上げたおせんべい「玉穂堂」。伝統を大切にしながらも、ココナッツせんべい、コーヒーせんべいなど新たな味を追求している。
田中屋せんべい総本家の魅力は、『どこにも真似できないおせんべいを作れること』だと田中社長は教えてくれた。事業を引き継いで20年、原材料や焼き方を研究し、より良くする方法を試行錯誤した成果だ。


④変化に対応し、進化し続ける組織
田中社長は、あえて事業計画を立てすぎず、常に変化に対応できる柔軟な姿勢を大切にしている。
「うちは事業計画をきっちり決めていないんです。いまは変化が多く、予測が難しい時代。そんな時代に、何かを決めるということは、その他の可能性がなくなるということ。変化が来た時に、素早く対応できなくなる可能性があります。私はその時、その時の変化に対応して、最良の判断をしたいと思っているんです。」
田中屋せんべい総本家では9年間、社員の離職者がゼロである。この定着率の高さには理由がある。それは表面的な理念や計画ではなく、社員一人ひとりが自律的に動き、働きやすい環境を自ら作り上げてきたことにほかならない。
「社員への研修をやめたことも、同じ理由です。『やらなきゃ』という義務感で取り組むことが、本当の成長につながるわけではないと思ったんですよね。今は日々の仕事のなかで、自分で考え、工夫しながら学んでいく風土が自然とできています。」
やらされるのではなく、自ら取り組む。日々のその積み重ねが、社員に愛される会社へ、愛される商品へと繋がっているのだ。

⑤せんべいの新しい価値を創る
「昔と比べるとせんべいの需要は無くなってきていると、感じることも少なくありません。そもそも興味を持たれにくいし、全国的に『おせんべいは美味しい』というイメージが薄れてしまっていると思います。」
田中社長は、こうした状況に危機感を抱いている。若い世代を中心に食文化が変わり、多様で魅力的な商品があふれているなかで、せんべいの魅力をどう伝えていくかが課題だという。
「せんべいに取り組むこと自体が難しい挑戦なんです。だからこそ、どうやってその価値を再評価してもらえるか、ランクを上げていくかがテーマです。」
社員たちもその想いに呼応するように、自発的にSNSで発信を始めている。田中社長は日々の取り組みと、その積み重ねを大切にしている。
「日々、商品をこういう風に作って、こうやって売っていこうと考えていく。それを積み重ねていると知らないうちに、理想にたどり着くんです。」
田中屋せんべい総本家の名前を広めること、ブランドとして確立させること、田中社長の想いはたくさんあるが、最終的な目標はもっと違うところにあるという。
目標として唯一掲げているのは、「従業員たちの給与を上げる」ことだ。働く人のことを考え、社員一人ひとりが安心して力を発揮できる環境をつくることで、会社全体の成長につながっているのだと田中社長は教えてくれた。
古くからの知恵や技術を大切にしながらも、新しい挑戦を恐れず、「せんべいの可能性」を示している。そうした姿勢こそが、田中社長の目指す理想の形であり、会社の未来をつくる力となっているのだ。

詳しい情報はこちら

 大垣市
大垣市 














