人と自然がつながる未来をつくる「やまのはたへ」を訪ねてみた。


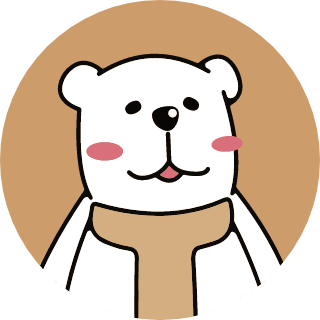
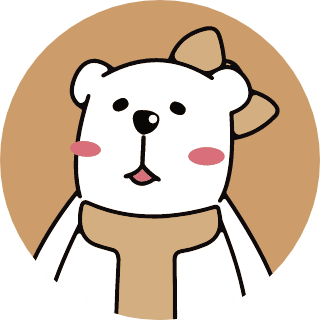
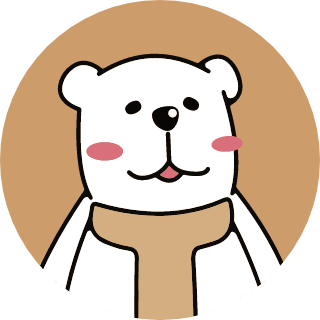
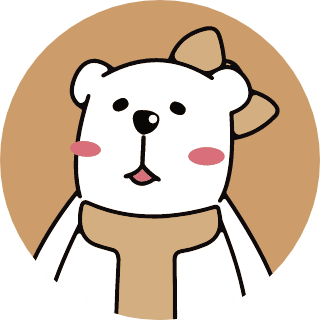
「誰もが山村と関われる社会を。」をミッションに掲げ、田植えや稲刈り、味噌作り、森の学校等の自然体験を通じて、まちの人や子どもたちに山村の魅力を伝える活動をしている。今回は、代表の酒向 一旭(さこう かずあき)様にお話をうかがった。
- “やまのはたへ”が生まれた背景と想い
- 役所職員から農の道へ。転機となった震災
- 子どもたちが“自分で動き出す”瞬間
- 自然体験がもたらす新たなつながり
- 日常としての山村へ。次なる挑戦
①“やまのはたへ”が生まれた背景と想い
美濃加茂市の山間部を拠点に活動している「やまのはたへ」。一風変わったこの社名には、酒向さんの深い想いが込められている。
「山と畑という意味も含まれているのですが、ここでいう『山』はこの里山のことを指していて、『はた』には『そば、近く』という意味があるんです。」
この名称の背景には、さらに明確なミッションがある。
「もともとこの会社のミッションとして『誰もが山村と関われる社会を。』という言葉を掲げています。山や畑といった自然に、多くの人がもっと身近に触れられるようにという願いを込めて『やまのはたへ』と名づけました。」
都市と山村の距離が広がりつつある現代において、誰もが山村と関われる社会をつくりたい。その想いが、この社名に凝縮されているのだ。


②役所職員から農の道へ。転機となった震災
現在は田んぼや畑を管理し、自然体験事業を展開している酒向さんだが、かつては役所で働いていた。独立に至るまでには、実に13年という長い時間が必要だった。
「役所に勤めていた頃は、出勤前に田んぼへ行って作業をしてから職場へ向かうという生活を、13年ほど続けていました。やりたいことも増え、だんだんと手が回らなくなり、事業の方に振り切ることを決めました。」
山村振興やまちづくりを担当する部署に所属していた酒向さんは、地域の現状を間近で見続けてきた。都市と山村の関係性に違和感を抱いたことが、田んぼを始める原点になったという。
「都市は消費者で、山村は生産者です。でも田舎が“お荷物扱い”されていて、都市へ集約させようという流れがあります。しかし、生産力があるのは山村です。田舎のことをもっと都市の人に理解してもらう必要があると感じました。」
そんな中、酒向さんが“自分で食料を生み出すこと”の重要性を強く意識するきっかけとなったのが、2011年の東日本大震災だった。
「震災ボランティアに何度か参加したのですが、現地は本当に食料がなくて。どうしてこんなに食料がないのかと強く感じ、自分自身で食料を生み出せる力の大切さを痛感しました。」
さらに、日本の農薬や肥料がほとんど輸入に依存していることを知り、外部資源に頼らない農業を志すようになる。有機農法を学び、落ち葉や米ぬかを使って堆肥を作りながら、農薬も肥料も使わない米作りに取り組んできた。
「堆肥は基本的に自分で作っています。米を作ると米ぬかが出るので、落ち葉や雑草と混ぜて堆肥にするんです。」
家族だけで始めた田植えは、友人を誘うようになり、体験したいという声も自然と増えていった。こうして小さな営みが広がり、いまの体験事業へとつながっていったのである。

③子どもたちが“自分で動き出す”瞬間
現在、やまのはたへでは田植えや稲刈り、味噌作りなど、さまざまな体験イベントを実施している。参加者は美濃加茂市内にとどまらず、岐阜県内はもちろん、名古屋等、県外から通う親子もいるという。中でも力を入れているのが、小学生向けの自然学校だ。
「今の子どもたちは、ゲームやテレビなど“誰かが作ったもの”で楽しむことが当たり前になっていると思うんです。でも自然の中には、決まった答えがあるわけではありません。自分が動かないと楽しめないので、“自分は何をしたいのか”という思考にガラッと変わるんです。」
与えられた遊びではなく、自分で考え、動き、楽しみをつくる――。そんな体験を子どもたちにしてほしいという想いがある。
「田植え体験でも、全員に“田植えをしよう”とは言いません。子どもたち自身が決めればいいと思っていて。生き物が好きな子はずっと生き物を追いかけていますし、黙々と田植えをする子もいれば、その様子をじっと眺めている子もいます。」
横並びで同じ行動を求めるのではなく、一人ひとりの興味を尊重する。その自由さこそが、子どもたちの主体性を育む。
また、子どもだけでなく、親御さんにとっても転機になることが多いという。
「泥だらけで遊ぶ姿を見て、『今まで気にしすぎていたかもしれない』と話してくださる親御さんもいるんです。イベントをきっかけに自分で田んぼを借りて農業を始めた方もいらっしゃいました。ここから新たな取り組みが始まっていくことが一番うれしいですね。」
移住した例もあり、小さな体験が人生の選択にまで影響を与えることもある。誰もが山村と関われる社会――そのミッションが、確かなかたちで広がり始めているのだ。


④自然体験がもたらす新たなつながり
やまのはたへの活動は、親子向けの体験イベントだけにとどまらない。近年は企業からの問い合わせも増え、活動の幅が大きく広がっている。
「新入社員研修で田植えをしたり、福利厚生として稲刈り体験を実施したりしています。田んぼの生き物について学ぶ講座や、防災キャンプなど、さまざまな取り組みをお任せいただく機会があります。」
企業で働く人にとっても、自然の中で体を動かす体験は貴重だ。経済を支える立場にある人々が自然に触れることで、山村の価値や役割を理解するきっかけにもなる。
「ニーズに合わせて体験内容をある程度カスタマイズできるのは強みだと思います。フィールドづくりを長年続けてきたので、山をどう整えればいいかという知識も経験としてお伝えできます。」
単なるイベントの実施にとどまらず、環境整備のノウハウまで提供できることが、酒向さんの大きな力になっている。保育園や小学校など教育機関からの依頼も増えており、自然との関わりを求める人の多さがうかがえる。
こうした活動を支えているのは、地域の人々とのつながりだ。
「自然と暮らすことは、ひとりではできないんです。みんなで協力して、この自然を生かしていく必要があります。山の整備も水路の管理も、同じ意識で取り組まないと暮らしていけません。地域の皆さんに支えていただきながら、一緒に進めています。」
現代では田舎のコミュニティが“煩わしい”と語られることもある。しかし酒向さんは、それは生きるために欠かせない要素だと考えている。地域の人々も、子どもたちが訪れて賑わう光景を心から喜んでいるという。


⑤日常としての山村へ。次なる挑戦
法人を立ち上げて3年目を迎えたやまのはたへ。ミッションの達成度について尋ねると、「まだ全然です」と酒向さんは謙虚に笑う。
「ただ、まだまだやりようはあると感じています。新しく取り組むべきことが逆に見えてきたので、そのあたりをこれから一つずつ進めていきたいですね。」
今後の展望として語ってくれたのが、ゲストハウスの運営だ。
「今はどうしても“イベントとして集まる”という形が中心になっています。でももっと日常的に、人が訪れられる場を作りたいんです。空き家を活用して、日常的にこの場所を体験できる施設を運営できたらと考えていて、すでに少し動き始めています。」
イベントだけでなく、日常的に山村と関わることができる場所をつくりたい。その背景には、この地域でひとつのモデルを完成させたいという思いがある。
「まずは自分の地域でしっかり実現させたいんです。そのうえで、他の地域で挑戦したいという人が出てきたら、その取り組みを支援できるような広がりを作っていきたいと思っています。」
とはいえ課題もある。農業だけでは費用面を十分にまかなうことが難しく、次の展開に必要な資金をどう確保するかが大きな壁だという。
「企業が田んぼや畑、山の整備や活用に関わりたいと考えてくれると、一緒に新しい取り組みが作れると思っています。そこから新しい出会いや、新たな挑戦が生まれるといいですね。」
企業との協働は、事業の幅を広げるだけでなく、地域に新たな動きを生み出すきっかけにもなっている。自然の中で行われる体験は、関わる人に気づきや変化をもたらし、その積み重ねが新しいプロジェクトへとつながっていく。
また、毎年新米の季節にはInstagramにてお米の注文を受け付けている。農薬も肥料も使わず、手間をかけて育てた貴重な一粒を、多くの人に味わってほしい。詳しくは「やまのはたへ」のInstagramで確認できる。
自然と関わる体験を求めている人、子どもに本物の体験をさせたい人、移住を考えている人は、ぜひやまのはたへを訪れてみてほしい。山村の豊かさと、そこで暮らす喜びをきっと実感できるだろう。

詳しい情報はこちら

 美濃加茂市
美濃加茂市 














